法人成りとは個人事業主が会社を設立し、それまで個人で行なっていた事業を法人に引き継ぐことです。一般的に、事業がある程度大きくなったタイミングで法人成りをするケースが多くみられます。
法人成りには多くのメリットがある一方で、注意するべきデメリットも存在します。「事業が大きくなったら法人成り」ではなく、メリット・デメリットの両方を把握した上で、法人成りをするか否かの検討が必要です。
今回は法人成りのメリット・デメリットを詳しく解説します。
法人成りのメリット
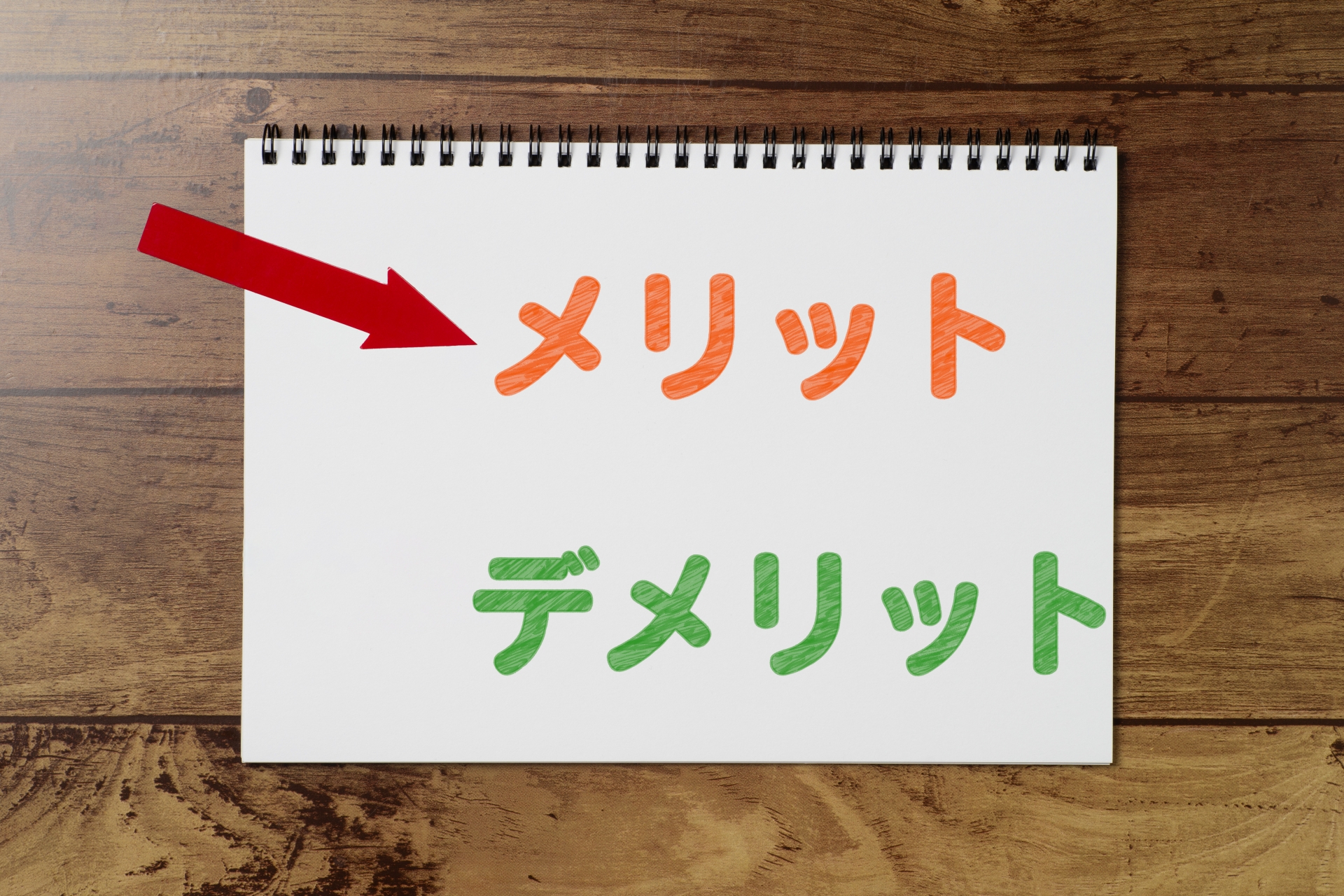
はじめに、法人成りのメリットを4つ紹介します。
個人事業主よりも節税できる可能性がある
法人成りの大きなメリットは、個人事業主よりも節税できる可能性がある点です。主な理由として以下の5つが挙げられます。
- 所得税は超過累進課税制度を採用しており所得が一定を超えると税率が上がる仕組みのため、事業所得が大きい場合は法人税の方が税額を抑えられる可能性が高い
- 個人事業主が赤字を繰り越せるのは最長3年だが、法人の場合は最長10年間の繰越が可能
- 個人事業主より法人の方が経費計上できる範囲が広い
- 自身への役員報酬を経費として計上できる
- 会社から受け取る役員報酬に給与所得控除が適用されるため、個人の所得税を抑えられる
事業規模がある程度大きくなった場合、個人事業主のままでいるよりも法人成りした方が節税につながります。
社会的信用を得やすくなる
同じ事業内容でも、個人事業主より法人の方が社会的信用を得やすい傾向です。理由として以下の3点が挙げられます。
- 法人は法務局への登記が必要であり登記事項は第三者が自由に閲覧できるため、会社の存在を明確に証明できる
- 法人の方が設立・廃業どちらも手間がかかるため、急に事業をやめるという事態が起こりにくい
- 法人と個人の資金は明確に区別されるため、プライベートが理由で事業のための資金が不足するリスクを抑えられる
実際に取引先を法人に限定している企業は多くみられます。また、社会的信用の得やすさから、法人の方が採用しやすい傾向も強いです。
決算のタイミングを自由に設定できる
個人事業主の会計期間は1月1日から12月31日と定められており、翌年3月15日までに確定申告および納税をする必要があります。事業によっては繁忙期と確定申告のタイミングが被ってしまい、負担が重くなりすぎる恐れがあります。
法人の場合は決算のタイミングを自由に設定可能です。繁忙期と決算期をずらすこともできるため、業務量が集中し過ぎてしまうのを防げます。
有限責任になる
事業における有限責任とは、出資金を上限に責任を負うことです。
個人事業主の場合、事業資産と個人のプライベートの資産は区別されません。事業のために融資を受けており、事業による収益だけでは返済しきれなくなった場合、個人の資産を処分してでも返済する必要があります。状況によっては債務整理が必要になるケースも起こり得ます。
会社の場合は原則として有限責任です。会社の資産を処分して借入金の返済をしきれなかった場合に、個人の資産にまで影響が及ぶことはありません。出資したお金が返ってくることはないものの、会社の借入金を個人が肩代わりする必要はないのです。
ただし、代表者による連帯保証を設定している場合は代表者個人に返済義務が移る恐れがあります。
法人成りのデメリット
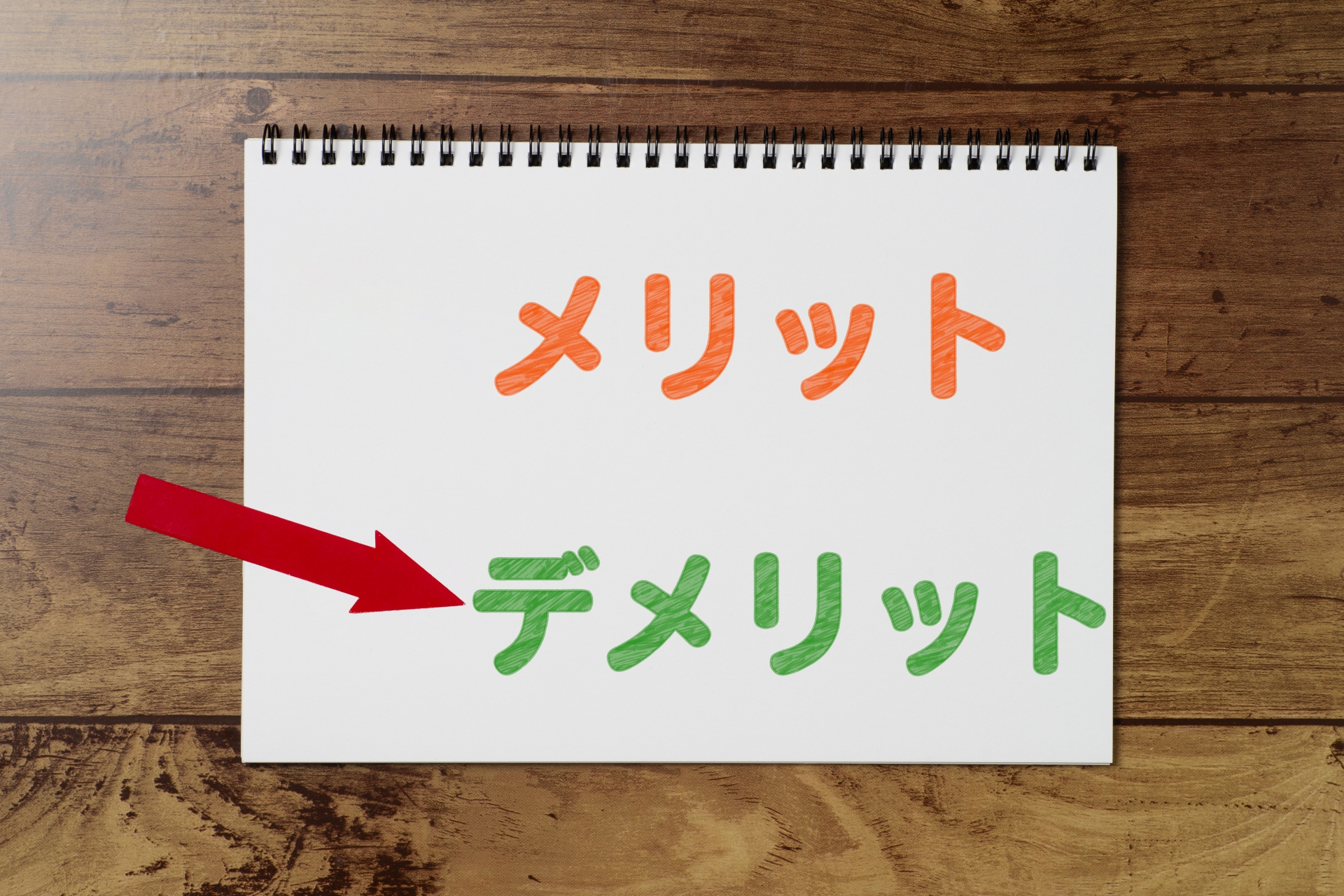
法人成りにはメリットだけでなくデメリットも存在するため注意が必要です。法人成りのデメリットを3つ紹介します。
会社設立に費用がかかる
個人事業主の開業に必ず発生する費用は特にありません。開業届の提出さえすれば、すぐに個人事業主として活動を開始できます。
一方、会社設立のためには以下のような費用がかかります。
- 定款用の収入印紙代
- 定款の謄本手数料
- 定款認証手数料
- 法務局に支払う登録免許税
上記は法定費用と呼ばれる、会社設立時に必ず発生する費用です。法定費用以外にも、専門家報酬や各種書類の発行手数料がかかるケースもあります。
株式会社の設立にかかる費用は最低でも20万円弱、相場は25万円〜35万円程度です。
個人事業主よりも手間がかかる
同じ事業内容でも、個人事業主より会社の方が手間がかかります。
前述のように、個人事業主の開業時にはコストがかかりません。開業届を提出すればすぐに事業活動を開始できます。一方で法人の場合は、定款認証・法務局への登記申請・税務署への法人設立届出書の提出など、さまざまな作業が必要です。
また、法人は社会保険への加入が必須です。会社設立すぐに社会保険関連の手続きをする必要があります。
事業を辞めるときの手続きも、個人事業主より法人の方が手間がかかります。事業を長く続けるつもりがないのであれば、法人成りを避けた方が良いでしょう。
会計関係のルールに違いがある
個人事業主と法人では会計関係のルールに違いがあります。法人ならではのルールとして以下の例が挙げられます。
- 交際費に損金算入限度額の定めがある
- 白色申告・青色申告に関係なく決算書の作成および提出が必須
- 赤字でも法人住民税の支払いが必要
個人事業主と同じように処理してしまうと誤りとなり、税務調査で指摘を受けてしまう恐れがあるため注意しましょう。




コメント