決算月はいつが良い?決算月に関するルールや決め方、変更方法を解説
会社は決算月を自由に決められます。しかし自由に決められるからこそ「決算月はいつにするのが良い?」「決算月を決めるときの判断基準が知りたい」と考える人も多いでしょう。
今回は決算月の決め方の例を3つ紹介します。決算月に関するルールや変更方法など事前に押さえるべき事項も解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
決算月に関する基本情報
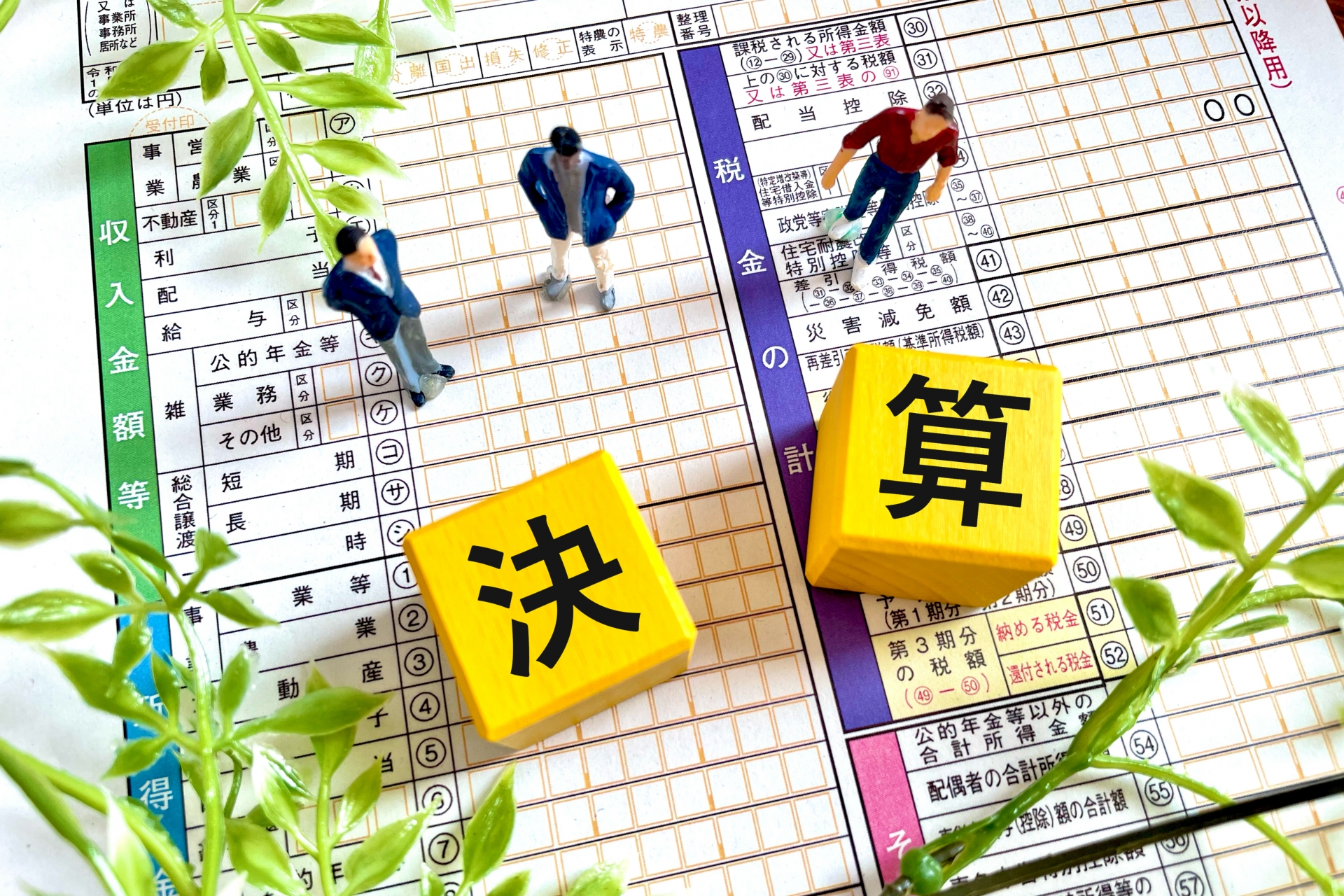
はじめに、決算月を決める上で押さえておくべき基本情報を解説します。
決算月とは
前提として、決算月とは事業年度の最終日や決算日が含まれる月のことです。「決算期」とも呼ばれており、事業年度における最後の月を指します。たとえば4月1日から翌年3月31日が事業年度の場合、3月が決算月(決算期)となります。
法人は事業年度の期末日段階、すなわち決算日の時点において決算手続きが必要です。また、決算日の翌日から原則として2ヵ月以内に、決算書の作成や法人税・消費税等の申告および納税を行う必要があります。
決算月や決算日に関するルール
法人の決算月や決算日に関する主なルールは以下の2つです。
- 事業年度は1年を超える期間には設定できないため、事業年度が1年超にならないよう決算月を定める必要がある
- 決算月や決算日を変えた場合は異動届を提出する。決算日を定款に記載している場合は株主総会による特別決議も必要
こちらの2点さえ守れば自由に決められます。たとえば1事業年度を1年未満の期間とし、1年のうちに決算月を2回設けることも可能です。また、決算日を月の末日以外にすることもできます。
ただし決算は手間がかかるため事業年度は1年になるように設定し、決算日も年1回にするのが一般的です。また、決算日は月の末日に設定するケースがほとんどといえます。
日本企業は3月決算が多い
国税庁が公開している資料の「決算期別の普通法人数」から、日本では3月を決算月とする法人が最も多いとわかります。次いで9月、12月を決算月とする法人が多いようです。
3月決算の法人が最も多い理由として、以下の3つが考えられます。
- 国や自治体が採用する会計期間が4月から翌年3月である
- 法改正や新制度施行は4月のケースが多く、3月決算であれば事業年度変更と法改正のタイミングを合わせられる可能性が高い
- 3月決算を採用している他の取引先と事業年度を合わせることでスムーズな取引が期待できる
とはいえ、3月決算を採用している法人は全体の2割弱です。3月決算が最も多いとはいえ、他の月を決算期にする法人の方が圧倒的多数となります。
「3月決算の法人が多いから自社も3月決算にしよう」と考える必要はありません。後述するポイントを押さえ、自社に適した決算月を設定しましょう。
決算月の決め方
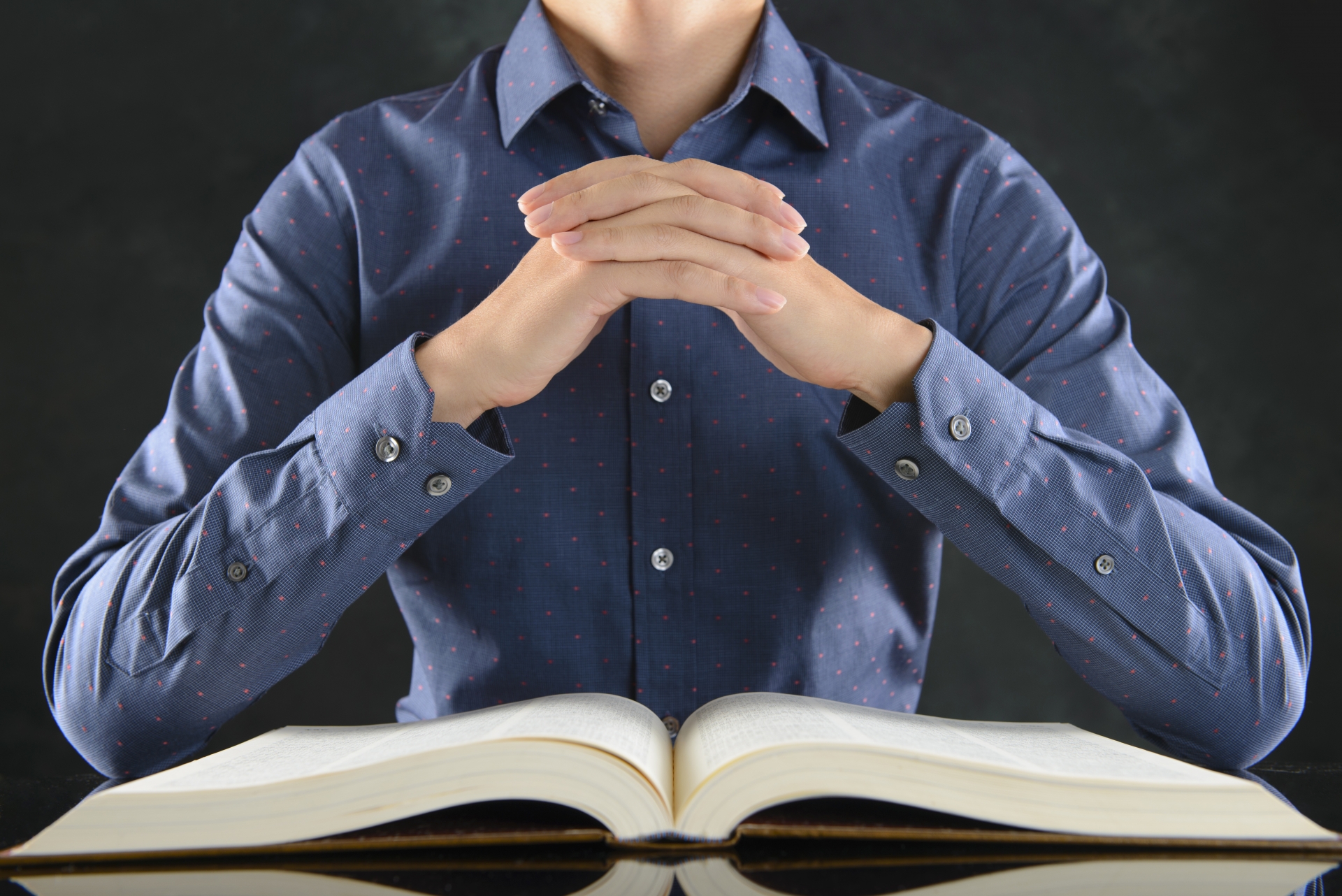
決算月の決め方に特別なルールはなく、前述の「決算月や決算日に関するルール」さえ守れば自由に決められます。
とはいえ、決算のタイミングは会社運営に大きな影響を与える可能性があります。トラブルのリスクを抑えるためにも、自社にとって負担の少ない時期を選ぶのが理想です。
以下では決算月を決める上で押さえたいポイントを3つ紹介します。
繁忙期を避ける
決算月は繁忙期と重ならないように設定しましょう。
繁忙期を避けるべき理由として以下の2つが挙げられます。
- 決算月から税務申告・納税が終わるまでは決算作業としてやるべきことが多いため、繁忙期と重なると負担が重くなりすぎる恐れがある
- 繁忙期は売上の変動が大きく、納税予測や節税対策がしにくい
繁忙期と決算月が重なると作業量が増えて負担が重くなり、ミスや漏れが起こるリスクが上がります。また、節税対策がしにくい点もデメリットです。
決算月は閑散期や、高額の売上が見込める月の1~2ヵ月前あたりにするのが良いでしょう。
高額の支出が発生する時期は避ける
資金繰りの面から考えると、高額の支出が発生する時期と決算月が重ならないようにするのが理想です。
前述のように、法人税や消費税は原則として決算日の翌日から2ヵ月以内に行う必要があります。すなわち決算月から2ヵ月以内に税金の支払いとして高額の支出が発生する可能性が高いです。
他の高額の支出と税額の支払いタイミングが重なってしまうと、資金繰りが悪化し経営に支障が出る恐れがあります。資金繰りに余裕をもたせるためには、高額の支出が発生するとわかっている時期の前後を決算月にするのは避けるのが無難です。
なお、高額の支出が発生するタイミングとして以下の例が挙げられます。
- 賞与の支払い時期
- 労働保険料の納付時期
- 源泉所得税の支払い時期
(納期の特例適用の場合は一度に半年分を支払うため、源泉所得税の支払いに伴い一時的に手元資金が少なくなる恐れがあります) - 設備投資や高額の仕入を行う時期
売上が見込める月の1~2ヵ月前にする
可能であれば、高額の売上が見込める月の1~2ヵ月前を決算月にするのが理想です。
「繁忙期を避ける」の中で、繁忙期は売上の変動が大きいため、納税予測や節税対策がしにくいと紹介しました。繁忙期に限らず、売上を読むのが難しい時期は決算月に適しません。
高額の売上が見込める月の1〜2ヵ月前を決算月に設定すれば、高額の売上が出るタイミングが期首に重なります。売上が伸びる時期から決算までに十分な期間を確保できるため、節税対策がしやすいでしょう。
ただし「売上が見込める月の1~2ヵ月前」という基準は、今回紹介した他の2つよりは優先度が低めです。忙しい時期や高額の支出が発生するタイミングと重なりそうな時は避けるのが無難といえます。
決算月の変更方法
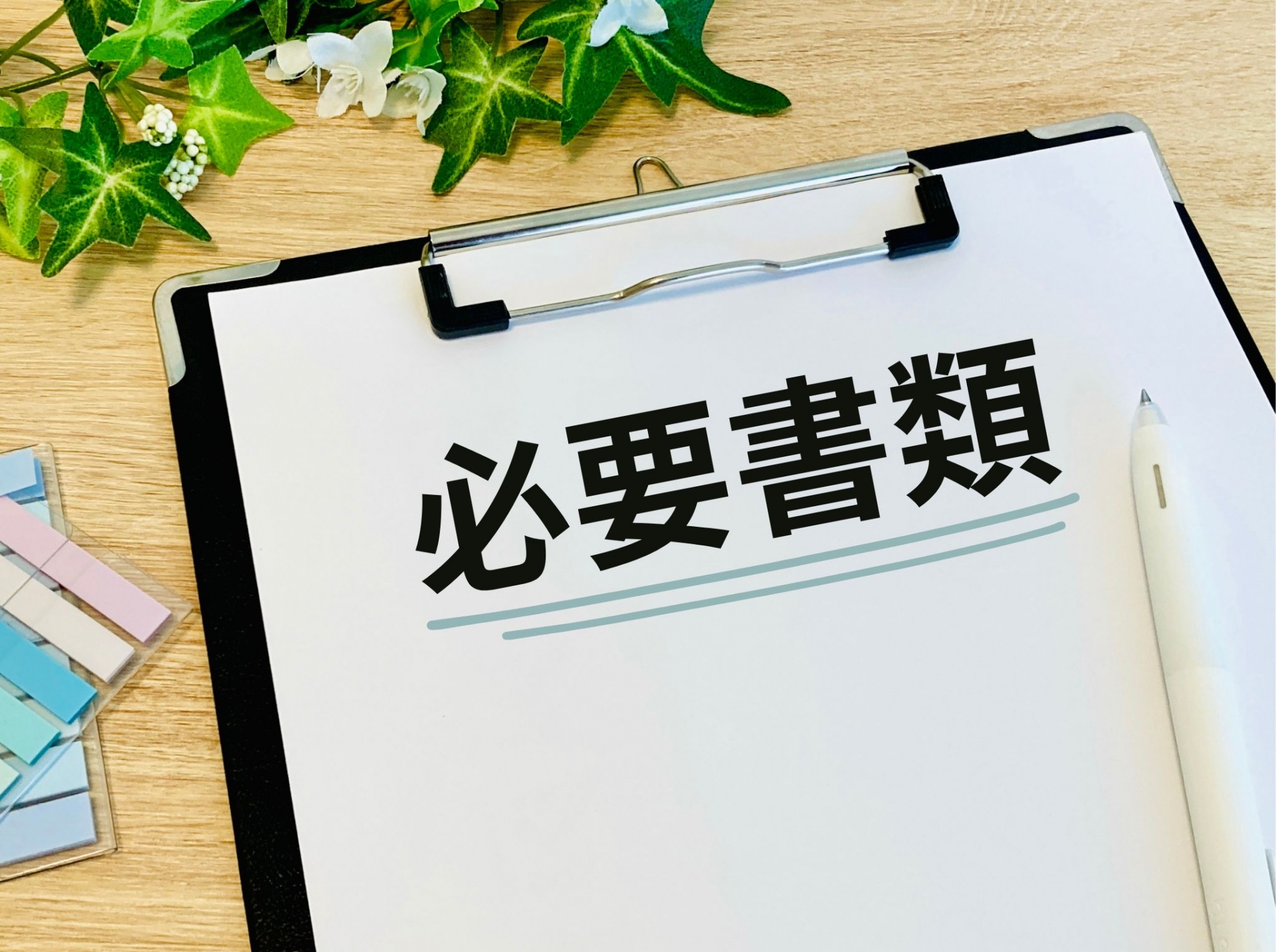
決算月は後から変更できます。
事業年度について定款に記載している場合は定款の変更が必要になるため、株主総会による特別決議が必要です。その際、株主総会の特別決議があった事実を証明するために議事録の作成が必須となります。
株主総会の後に、税務署、都道府県税事務所、市町村役場に異動届の提出が必要です。あわせて、変更後の定款および株主総会の議事録も提出する必要があります。




コメント