源泉徴収とは給与、賞与、一定の要件を満たす報酬等を支払う際に、支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引くことです。源泉徴収によって差し引いた所得税等は期日までに納付する必要があります。
給与や報酬の支払いを行う事業者は原則として源泉徴収義務者となります。源泉徴収の義務を怠った場合や手続きに不備や漏れがある場合、ペナルティの対象になる恐れがあるため注意しましょう。
今回は源泉徴収について、事業者が押さえるべき事項を詳しく解説します。
源泉徴収とは
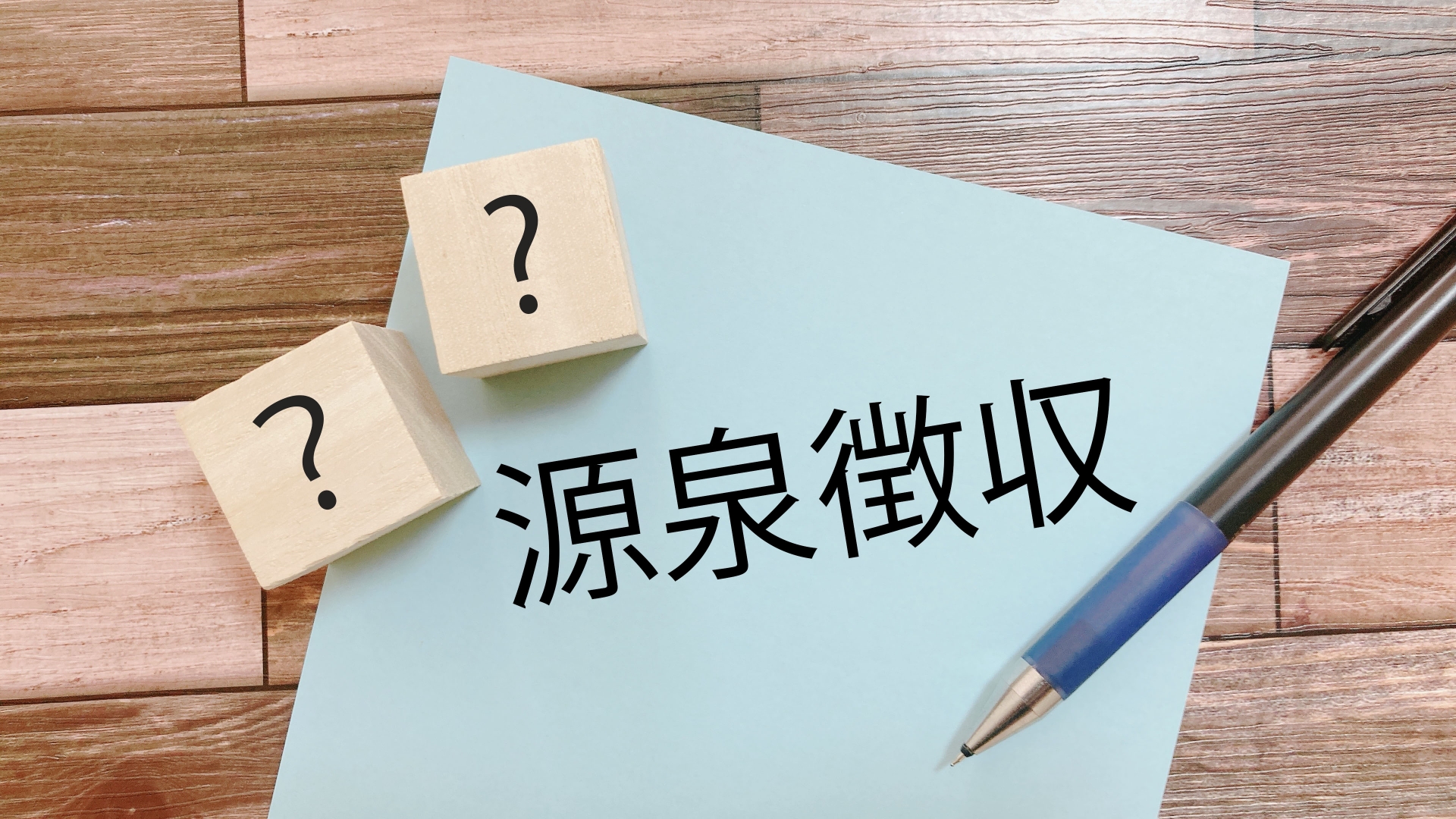
源泉徴収とは事業者が給与や報酬等を支払う際に、支払額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引くことです。源泉徴収によって差し引かれた所得税等を「源泉徴収税」や「源泉所得税」と呼びます。
源泉徴収税は原則として、源泉徴収を行なった月の翌月10日までに納付が必要です。
源泉徴収の対象となる所得の範囲
源泉徴収の対象となる所得の範囲は、報酬等を受け取る者が個人と法人どちらであるかによって異なります。それぞれ詳しく紹介します。
【個人の場合】
個人の場合に源泉徴収の対象になる支払いは以下の通りです。
- 給与所得
- 退職所得
- 所得税法等で定められている一定の報酬
- 利子
- 配当
- 公的年金
- 保険契約に基づく年金
このうち事業者に関係するのは1〜3となります。3に該当する支払いの具体例は以下の通りです。
- 原稿料、講演料
- 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の特定の士業に支払う報酬
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロスポーツ選手に支払う報酬
- モデルや外交員に支払う報酬
- 映画、演劇その他芸能に関する報酬、テレビ放送の出演料
- ホテル等の宴会で接待を行うコンパニオンや、バーなどに勤めるホステスに支払う報酬
- 役務の提供を約し、一時に支払う契約金
- 広告宣伝を目的とした賞金や、馬主に対して支払う競馬の賞金
【法人の場合】
報酬を受け取るのが法人であれば、以下が源泉徴収の対象になります。
- 馬主である法人に支払う競馬の賞金
- 利子
- 配当
源泉徴収義務者となる条件
源泉徴収義務者となるのは、給与や報酬を支払う事業者です。
ただし、常時雇用するのが2人以下で、税法上の家事使用人のみの個人事業主には源泉徴収義務がありません。雇用している家事使用人に対する給与も対象外となります。外注費の支払いはあるものの従業員を雇用していないケースでも、同じく源泉徴収は不要です。
常時雇用するのが2人以下であっても、家事使用人に該当しない一般の従業員であれば源泉徴収を行う必要があります。
法人は、給与等の支払いをしていなくても必ず源泉徴収義務者となります。
源泉徴収税の納付期日
最初に紹介したように、源泉徴収税は原則として源泉徴収を行なった月の翌月10日までに納付する必要があります。
しかし例外として、以下の要件を満たす場合は年2回にまとめて納付する特例制度の適用が可能です。
- 給与の支給人員が常時10人未満である
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出している
納期の特例を適用した場合、納付期日は以下のようになります。
- 1月~6月に支払った所得から源泉徴収した分:7月10日
- 7月~12月に支払った所得から源泉徴収した分:翌年1月20日
なお、納付期日を過ぎてしまうと以下のような附帯税の対象になるため注意が必要です。
- 延滞税:納付期日を過ぎた場合に課される。利息のような性質をもつ
- 不納付加算税:源泉徴収税を期日までに納付しなかった場合に課される
源泉徴収事務の内容
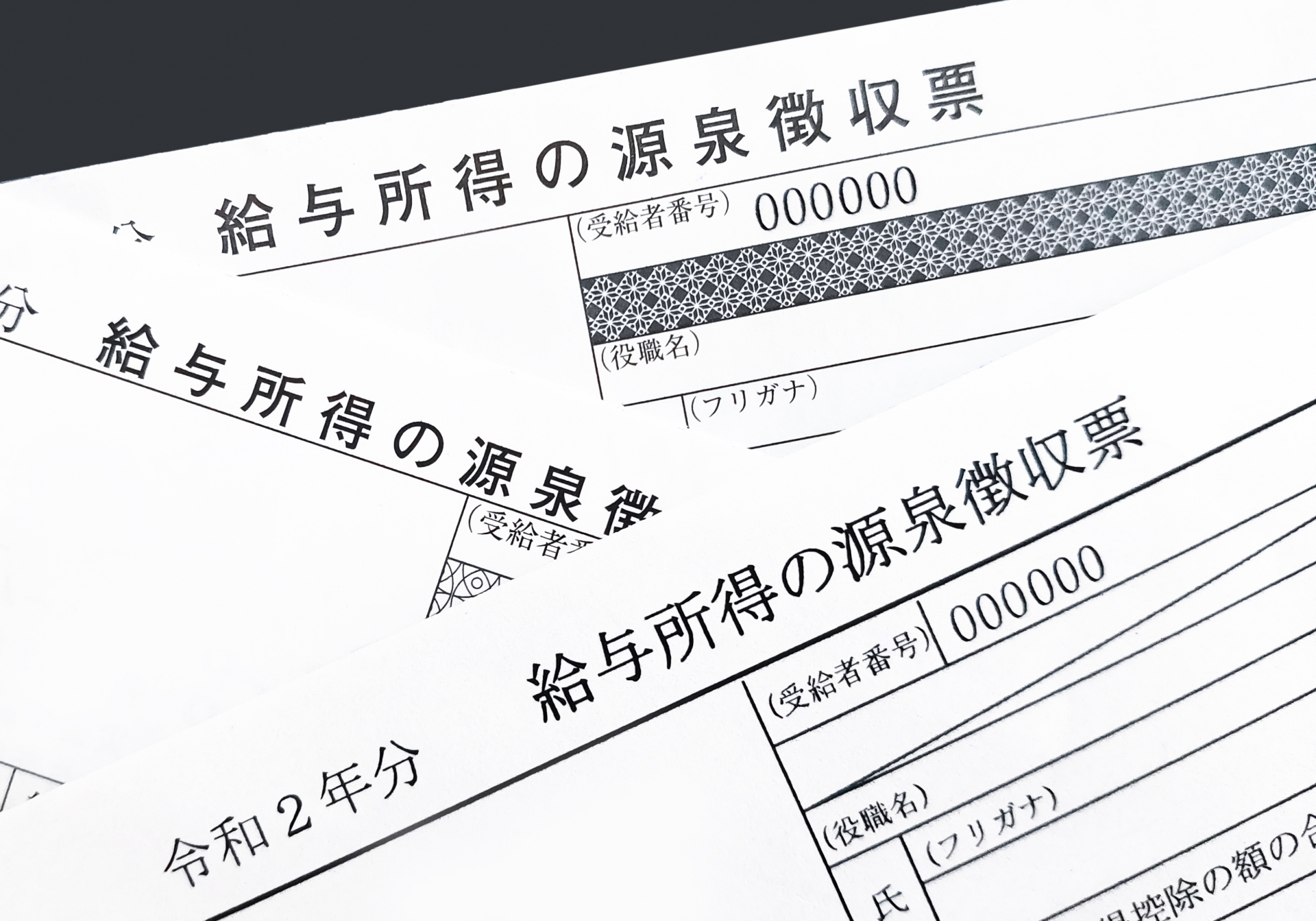
源泉徴収義務者は事前の準備から年末調整まで、さまざまな作業を行う必要があります。この章では源泉徴収事務の内容について解説します。
※今回紹介するのは給与および報酬の源泉徴収に関する作業内容です。
源泉徴収を行うための準備
まずは、事前に行うべき準備を3つ紹介します。
1つ目は「給与支払事務所等の開設届出書」の提出です。新たに給与の支払いを始めることで源泉徴収義務者になるときに提出する必要があります。提出期限は給与支払事務所等を開設してから1ヵ月以内です。
2つ目は従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうことです。従業員の扶養親族数や税区分を確認するために必要となります。入社時に空欄の様式を共有し、期日までに提出してもらう方法をとるケースが多くみられます。
3つ目は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出です。前章で紹介したように、一定の要件を満たす場合は源泉徴収税を年2回にまとめて納付する特例を活用できます。納期の特例の適用を受けるためには、事前に申請書の提出が必要です。
源泉徴収の実施
毎月の給与や報酬から源泉徴収を行います。
最初に、源泉徴収では支払額に応じた所得税等を差し引くと紹介しました。こちらの計算で使う支払額は額面ではなく、非課税の通勤手当や社会保険料などを差し引いた手取り額のため注意しましょう。
給与から差し引く源泉徴収額は国税庁が公開する「源泉徴収税額表」で確認可能です。報酬の源泉徴収額は業種によって計算方法が異なるため個々にご確認ください。
源泉徴収税の納付
源泉徴収した所得税等は、翌月10日または納期の特例の期日までに納付しましょう。納期を過ぎてしまうと、前章で紹介したように延滞税や不納付加算税が課せられます。
年末調整
年末調整とは給与等から差し引いた源泉徴収税額と、実際の所得税額の差額を調整するための手続きです。給与等の支払いを行う源泉徴収義務者は年末調整の作業も行う必要があります。
過不足の精算は12月または翌年1月の給与支払い時に行うのが一般的です。また、年末調整の過不足精算とあわせて源泉徴収票の交付も行います。




コメント